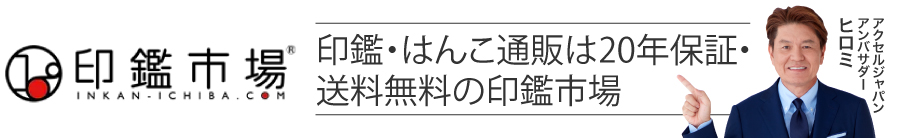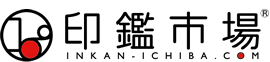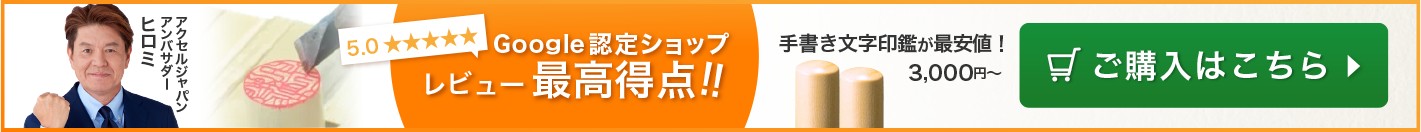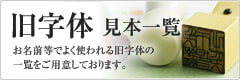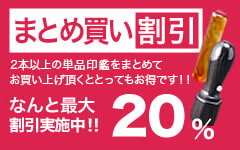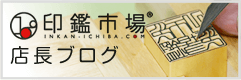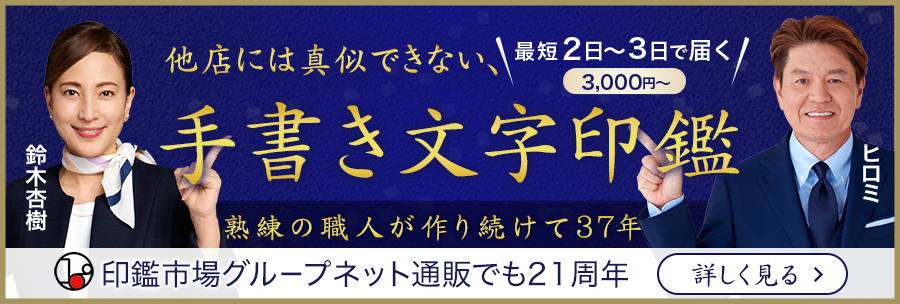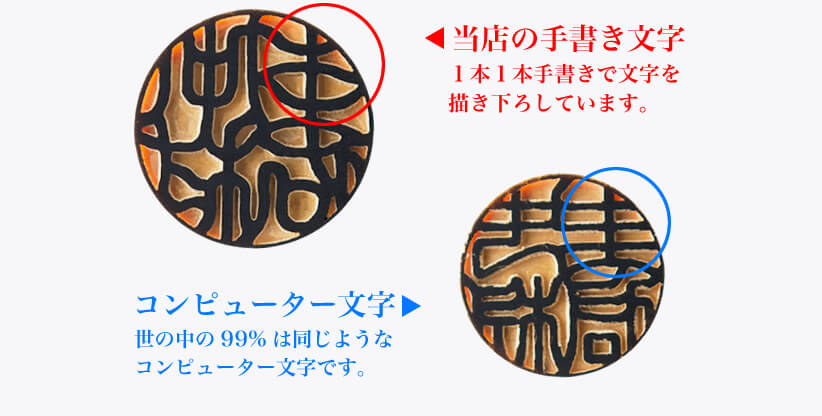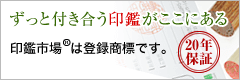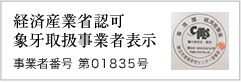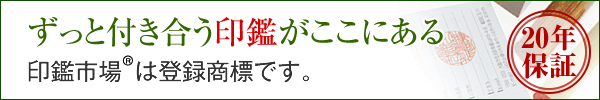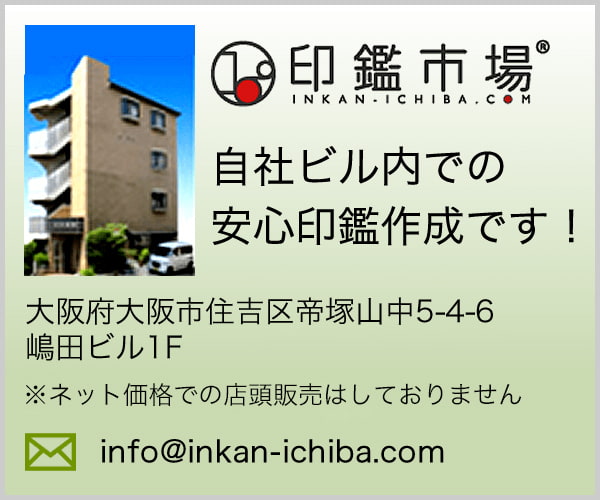2021.5.20カテゴリー:印鑑について
日常生活で当たり前のように使っているハンコについて考えたことはあるでしょうか。
身近な存在であるにもかかわらず、ハンコの歴史や文化を知らない人は意外と多いです。
そこで今回は、ハンコの歴史や文化がいつから始まったのかについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□ハンコとは?
会社では契約書や領収書、休暇届や始末書など、さまざまな書類でハンコが必要です。
会社でなくても契約の際や荷物を受け取る際など、ハンコは多くの場面で活躍しています。
そもそもハンコとはどういったもののことを指すのでしょうか。
まずは、ハンコについて説明します。
ハンコと聞くと、絵や文字が刻まれているものから印鑑や認印、実印まで、さまざまなものを思い浮かべるでしょう。
広い意味ではこれらすべてをハンコという言葉で言い表せますが、私たちは普段から言葉を使い分けています。
ハンコと印鑑という言葉はどちらもよく使用されますが、その意味には違いがあります。
印鑑は紙に写った印影で、捺印後に残る印のことです。
正式に公に提出している特定の印影のことを印鑑といいます。
一方で、ハンコは名前の文字が刻まれた本体の方を指し、正式には印章と呼ばれています。
しかし、この2つは同じものであると考える人も多く、言葉の厳密な意味の違いにこだわる必要はないでしょう。
□ハンコの歴史について知っておこう!
ここまでは現代のハンコについて紹介しました。
言葉の意味の細かな違いは、知っておくと役に立つことがあるかもしれません。
ここからは、ハンコの歴史がいつから始まったのかについて紹介します。
*ハンコの起源
ハンコの起源は紀元前のメソポタミアにあるといわれています。
今から5000年ほど前のこの時代のハンコは、現代で見られるような形ではなく、筒形の側面に模様や絵が刻まれていました。
人々は出来上がった筒形のハンコを粘土に転がすように押し付けて使用していました。
この当時は権力を持っている人の書簡を封印し、印をつけるために使用されていました。
*世界へと広まる
メソポタミアで発達したハンコはエジプトやローマ、ギリシャなど、各地に広がり、シルクロードを経てアジアにも伝わりました。
アジアへ伝播したハンコは、中国で文化が大きく発達します。
ハンコは中国で盛んに使用され、官印制度として正式に統一されました。
秦の始皇帝がハンコ用の文字を定め、積極的に政治に利用しました。
その後、漢の時代にハンコはさらに広い範囲で使用されるようになり、信頼や統治の証として諸国の王へ贈られることもありました。
*中国から日本へ
世界に広まり中国で大きな発展をしたハンコは、日本にも伝わりました。
日本最古のハンコは、北九州で発見された金印です。
奈良時代では、大宝律令によって公にのみハンコの使用が認められ、個人的なハンコは国家の許可が必要でした。
平安時代では貴族が個人的なハンコを使用できるようになりました。
その後武士が台頭するようになると、花押(かおう)と呼ばれる書き判が広まり、次第にハンコを個人の証明として使用することが定着していきます。
戦国時代では、各地の武将たちは自分だけのハンコを作りました。
織田信長の天下布武や上杉謙信の虎の印などが有名です。
*制度が確立される
明治6年に明治新政府が実印を捺す制度を定め、印章が正式に市民権を得ました。
ここからが近年のハンコ文化の始まりです。
10月1日に制度が確立されたため、その日は印章の日とされています。
制度としては浅く感じるかもしれませんが、ハンコは古くから国や支配者の正式な権力の象徴として大切に扱われてきたのです。
□ハンコの文化とは?
ここまでハンコの歴史について紹介しました。
日本ではハンコの文化が今も根強く残っていますが、海外ではあまり使われなくなりました。
ここからは、ハンコの文化について説明します。
上記でも述べたように奈良時代では、ハンコの使用が公にのみ認められていました。
このころは一般庶民にハンコの文化はまだなく、政府高官の中でも位の高い人だけがハンコを使えました。
奈良時代のハンコの文化は律令制の衰退に伴って、次第に衰退していきました。
戦国次第にハンコの文化が再興し、江戸時代には庶民が使用し始めます。
戦国の時代はほかの地域との通信や取引が増えたため、再び各地の大名がハンコを使用するようになりました。
江戸時代には商工業がさらに発展し、庶民の間でのハンコの使用が活発になりました。
このように人と人とのかかわりが強くなるにつれて、ハンコの需要は高まっていったのです。
□まとめ
ハンコの歴史や文化がいつから始まったのかについて解説しました。
ハンコは古くから国や支配者の正式な権力の象徴として大切に扱われてきました。
また、ハンコは時代の流れとともに盛んに使用されたり、衰退したりを繰り返してきました。
ハンコづくりでお悩みの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。