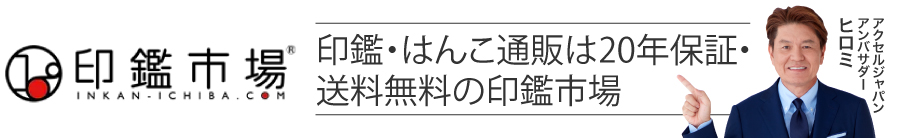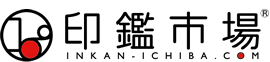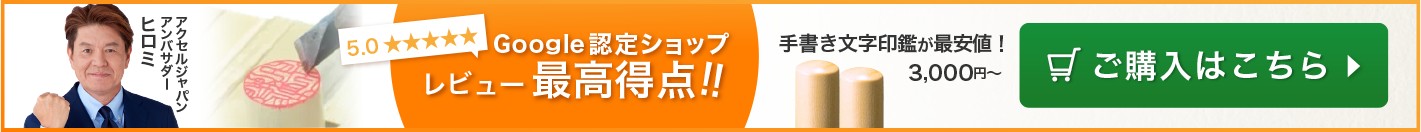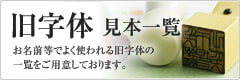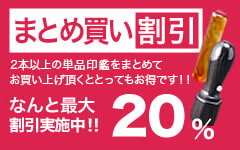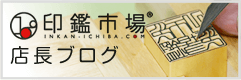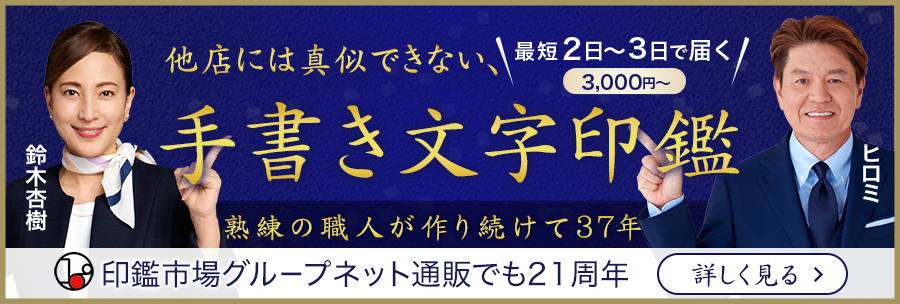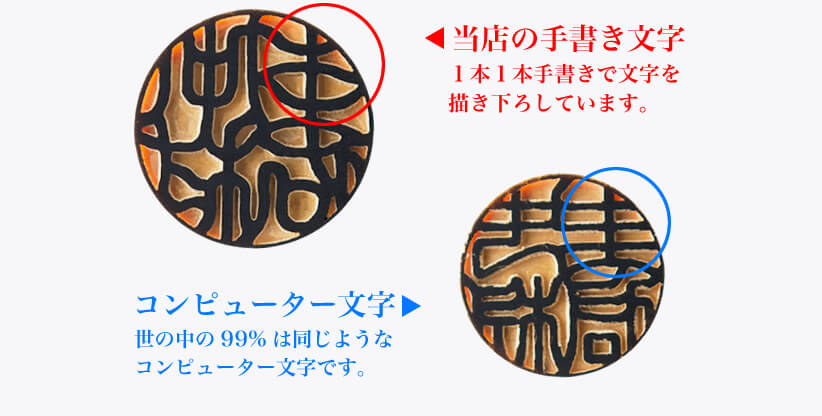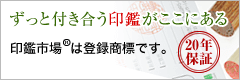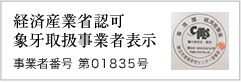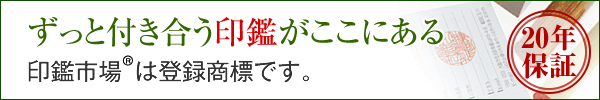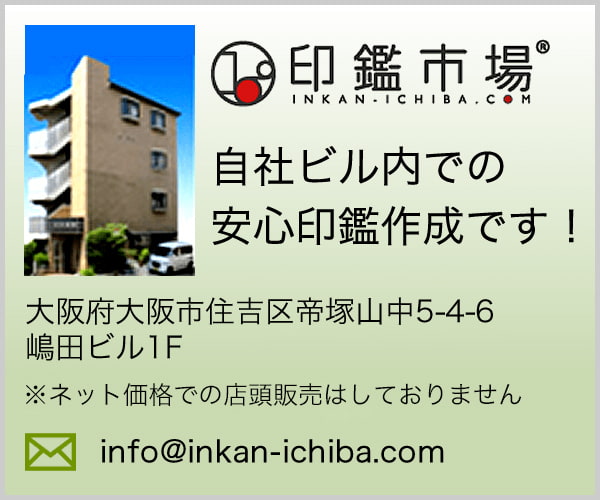公開日:2021.6.20カテゴリー:印鑑について
更新日:2024.4.22
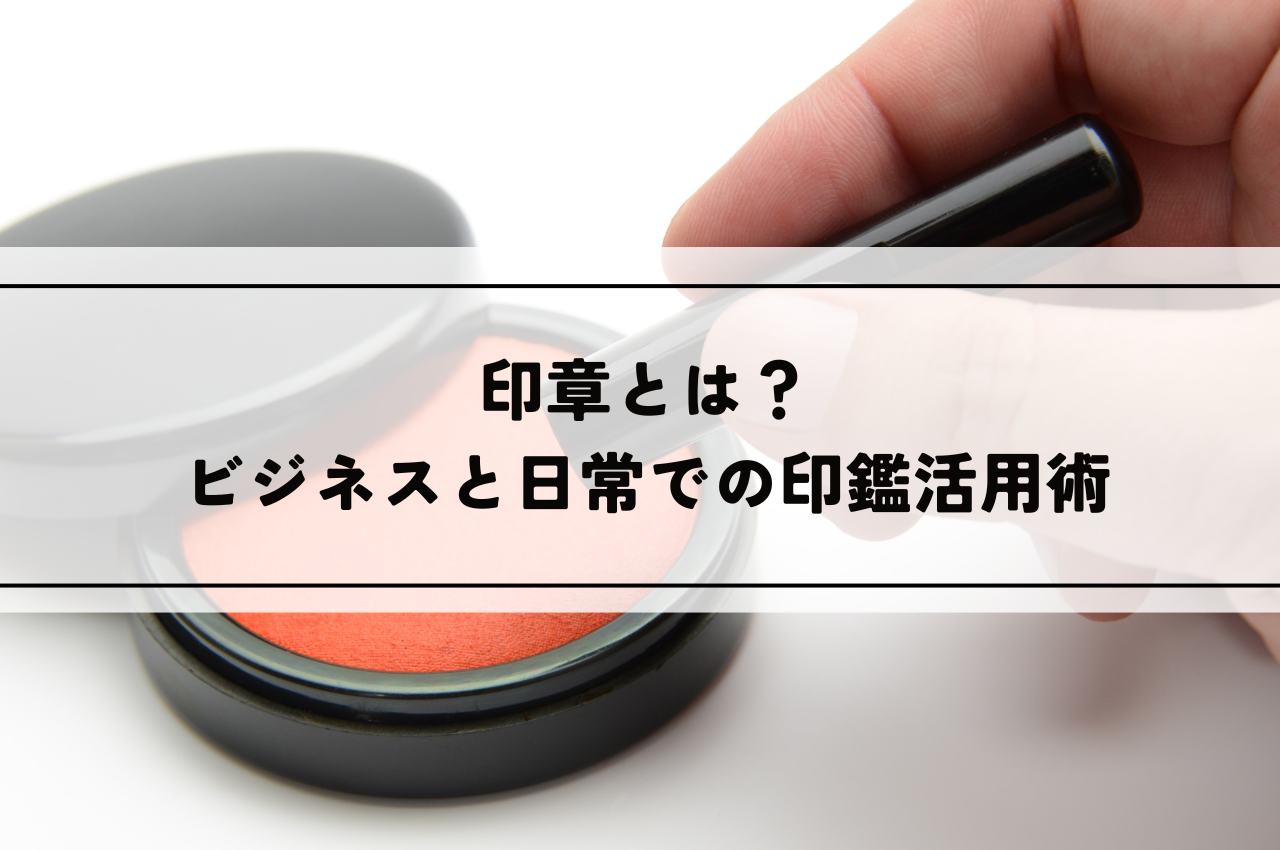
何気なく日常でハンコや印鑑という言葉を口にしていませんか。
これらには、微妙な違いがあります。
ハンコの種類も様々でややこしく、誤ってハンコに関係する用語を使っている方も多いかもしれません。
今回はハンコにまつわる用語の整理をしていきます。
□意外と知らない事実!印鑑とハンコの違いとは?
印鑑とハンコの違いをご存じでしょうか。
同じものでないのかと思われる方も多くいらっしゃるでしょう。
実は、印鑑とハンコには大きな違いがあります。
ハンコ屋界隈ではこの違いは常識として知られています。
印鑑とは、官公庁や銀行で登録した印影のことを指します。
ちなみに官公庁で届け出るのは実印で、銀行に届け出るのは銀行印と呼ばれます。
また印影とは、押印した時に紙に朱肉が写されて浮かび上がるマークのことを指します。
これに対して、ハンコとは押印の時に手に持つ本体のことを指します。
正式名称では印章と呼びます。
□用途によって異なるハンコの種類を紹介します!
ハンコは用途によって複数の種類があります。
ここでそれぞれのハンコの違いについて解説します。
1つ目は、実印です。
重要な契約書は、真に本人が自らの意志によって作成したという証明が必要です。
実印はその証明のために使われます。
大きなお金が動く際に実印の出番が来ます。
具体的な使用場面の例としては、家や車を買った時や、融資を受ける時、保険に加入する時などが挙げられます。
多くの場合、契約の際には実印と印鑑証明書の提出が求められるでしょう。
印鑑証明書は、役所に印鑑登録をするとすぐに発行できます。
実印と印鑑証明書は財産や権利を守る大事なものなので、厳重な管理が必要です。
実印は、市区町村に届け出て印鑑登録をしたものです。
実印は1人につき1つしか登録できません。
また、苗字が同じ家族でも誰か1人の実印を他の家族が自分のものとして使うことは認められませんので、注意してください。
実印は偽造される危険性への配慮から、フルネームで作る方が多いです。
また、印鑑登録できる印影の条件が定められている市区町村もあるので、大きさや絵柄については注意して作成して下さいね。
2つ目は、認印です。
確認しましたという意味を持つハンコです。
普段の生活での利用場面が最も多いものでしょう。
具体的な使用場面の例としては、役所に通常の書類を提出する時、荷物を受け取った時、会社で書類を確認した時などが挙げられます。
登録する必要もないため、既製品のハンコをそのまま使用します。
3つ目は、銀行印です。
銀行印は名前にある通り、銀行で登録したハンコのことです。
具体的な使用場面の例としては、口座を開設する時が挙げられます。
かつてATMがなかった時代は、入出金をする際にも必要なものでした。
使用する場面が少なくなってはいるものの、窓口での取引では必要となる場合も依然として多くあります。
4つ目は、シャチハタです。
朱肉がなくても押せるハンコを指してシャチハタという言葉を使っているのが一般的でしょう。
実は、シャチハタとはハンコ本体のことではなくてメーカーの名前です。
シャチハタというメーカーの、朱肉がなくても押せるハンコが爆発的にヒットしたことが由来です。
インクが本体に内蔵されているので、キャップを開けたらすぐに押せて便利です。
具体的な使用場面の例としては、荷物を受け取る時や会社の書類を確認する時が挙げられます。
□まだまだ気になる微妙な違い!ハンコとサインの関係についてご存じですか?
日本でハンコは日常的に使用されますが、これは日本独特の文化でしょう。
海外においては、ハンコではなくてサインを使用することがほとんどです。
日本でもサインする場面はありますよね。
中には、サインとハンコを同時にするものもあります。
日本でのサインとハンコの関係が気になりませんか。
以下でその関係について解説します。
突然ですが、サインは日本語でなんと訳すでしょうか。
署名か記名かで意見が分かれるかもしれません。
実際に署名と記名には違いがあります。
サインといった場合、署名を指します。
署名は必ず、自筆で行います。
これに対して記名は、他人に書いてもらっても認められますしハンコを押しても認められるでしょう。
響きは似ていますが、重要な違いなので頭の片隅に入れておくことをおすすめします。
サインとハンコで法律的な効果が異なるかと言われると何も変わりません。
もともとこれらがなくても契約は成立しますし、その契約の効果は有効です。
なぜ使用するのかについては、自分の意志で契約を結んだことの確たる証拠としての意義があるからです。
そのため、サインやハンコを使用する際には慎重に行ってくださいね。
□印章、印影、印鑑の違いとは?
印章、印影、印鑑。
これらは日常的に使用されてることが多いですが、その違いについて詳しくは知られていないことが多いです。
この章では、これらの用語の正確な定義と適切な使い分けについて解説します。
*印章
印章とは、一般に「ハンコ」と呼ばれる物理的な物体、すなわちハンコ本体のことを指します。
木製、チタン、牛のツノなど、様々な素材で作られています。
印章は、その形状や材質により多様なデザインが存在し、個人の象徴としても使用できます。
例えば、ビジネスシーンでは、契約書や重要書類に押印する際に使用されます。
*印影
印影とは、印章に朱肉を付けて紙などの媒体に押し付けた際に残る跡のことです。
朱肉の色、印章の形状、押す力の加減によって、印影の見た目が変わります。
印影は、文書や契約書において、個人や企業の意志の承認や確認の証として機能します。
*印鑑
印鑑とは、特定の印章の印影を指す用語で、特に公的な登録に使用されるものを指します。
例えば、銀行印や実印など、法的な効力を持つ文書に使われる印鑑は、その印章の印影を指すものです。
一般的に「印鑑」と呼ばれるものは、このような法的な効力を持つ印影を意味することが多いです。
印章や印影を総称して印鑑と呼ぶこともありますが、専門的な文脈ではそのような使い方は適切ではありません。
□印鑑とハンコの語源について紹介!
みなさん、語源の違いについてご存知でしょうか。
今回は、それぞれの語源の定義を明確にします。
印鑑の語源は、台帳(=鏡)が由来となっており、ハンコが本物か偽物かを確認するために使用されていました。
のちに、その台帳が「印鑑」として認知されるようになり、さらに本物のハンコで押された印影も「印鑑」と呼ばれるようになりました。
印鑑を照合してハンコの信憑性を確認する方法は、現に銀行でも取り入れられています。
一方で、ハンコの語源については、真相が明らかになっていません。
以下が現時点で考えられる諸説になります。
・江戸時代に有名な版画に使用する板が、「板行(はんこう)」と呼ばれるようになり、それが起因して、「ハンコ」となった。
・「版を押すことを行う」ということばの「版行」に由来して、「ハンコ」になった。
・版行を使用して書物を印刷することと、印象で捺印することの見分けがつかなくなったため、印章が「ハンコ」として認識されるようになった。
□知っておきたい印鑑の歴史をご紹介!
*日本で最も古い印鑑ってなに
現時点では、後漢の光武帝が日本に送った金印が最も古い印鑑だとされています。
この金印には、「漢委奴国王」が印字されており、高校で習う日本史の教科書にも掲載されているほど、有名ですね。
しかし、日本最古の印鑑は裏付けが取れる資料が不足しているため、まだ明らかになっていません。
*印鑑が正式に制度として取り入れられた
奈良時代に初めて、印鑑が制度として取り入れられたと伝えられております。
平安時代になってからは私印が許可され、代表的な例として藤原氏の私印が挙げられます。
当時は、印鑑の利用が公式に許可されていなかったため、離婚届や売買証文等を締結する場合は、自ら署名したり、人差し指を使って点を打つ画指(かくし)が使用されていました。
*10月1日は印象の日
ご存知ない方が多くいらっしゃると思われますが、10月1日は「印章の日」とされ、様々なイベントが印鑑業界内で催されています。
ちなみに、「印章の日」は太政官布告に由来しており、初めて実印の価値が法的に認められました。
実印を押すことが制度化されたことにより、認印や実印が広く普及するようになりました。
□印鑑登録と印鑑証明の登録方法をご紹介!
*個人で印鑑登録をし、印鑑証明書を発行する場合
個人で印鑑登録を行う場合は、実印用の印鑑と顔写真付きの身分証明が必要になります。
登録を行う際、15歳以上の本人であり、かつ印影が本名でサイズが8mmから25mmであれば、即日での登録が可能になります。
しかし、登録できる実印の基準は、各自治体によって異なりますので、事前に電話やホームページで確認することを頭に入れておきましょう。
印鑑証明書は、印鑑登録を行うと発行されます。
さらに、印鑑登録証、顔つきの身分証明証、手数料の3点が揃っていれば、その日のうちでの発行が可能となります。
*法人の場合
法人で実印(=代表者印)登録をする際は、法人の本店所在地にある法務局に申請を行ってください。
そこで必要になるものは、代表者印、代表者本人の実印、発行後3か月以内の本人実印の印鑑証明書の3点です。
注意点として、代表者本人のハンコが実印として認められなかったら、再作成に時間がかかってしまう可能性があります。
そのような事態を防ぐために、事前に本人の印鑑登録と印鑑証明書を発行してから、代表者の登録を行うように意識してください。
また、印鑑証明書は最寄りの法務局での発行が可能です。
受け取りの際は、申請書に会社の商号、住所、印鑑提出者の役職、氏名、生年月日、印鑑カード番号を記入の上、手数料分の収入印紙を添えて提出してください。
□印鑑照合の方法とその重要性
印鑑照合は、文書の真正性を確認するために不可欠なプロセスです。
このプロセスでは、印鑑証明書に記載された印影と、提出された文書に押された印影が一致するかを確認します。
ここでは、その方法と重要性について詳しく見ていきましょう。
1:平面照合
平面照合は最も基本的な方法で、印鑑証明書と文書の印影を並べて比較します。
この方法は裁判所でも認められていますが、細かな違いを見逃すリスクもあります。
特に、印影が微妙に異なる場合、人の目では完璧に識別するのが難しいのです。
2:残影照合
残影照合は、印影を重ね合わせ、高速でめくることで生じる残影を利用します。
この方法は、微細な違いを捉えるのに有効ですが、熟練を要する技術です。
3:コンピュータを使用した照合
現代技術の進歩に伴い、コンピュータを利用した照合方法も普及しています。
この方法では、印影をスキャンしてコンピュータで比較分析します。
精密な比較が可能であり、人間の目には見えない微細な違いも検出できます。
4:拡大鏡を使用した照合
拡大鏡を使った照合では、印影の細部を拡大して確認します。
この方法は、特に細かなディテールを比較する際に有効です。
5:透かして照合
透かして照合は、印影を重ね合わせ、透明な光に透かして確認する方法です。
この方法も、細かな違いを視覚的に捉えるのに役立ちます。
これらの方法は、単独で使用されることもありますが、より確実な照合のためには複数の方法を組み合わせることが一般的です。
印鑑照合の正確性は、法的文書の信頼性を保証する上で非常に重要です。
技術の進歩により、これらの方法はさらに洗練されていくでしょう。
□ビジネスと日常での印章・印鑑の効果的な使用法
ビジネスや日常生活で印章と印鑑を使う場面は多く、その効果的な使用方法は多岐にわたります。
適切な選択と管理は、日々の業務や生活を円滑にし、同時に個人や企業の信頼性を高めることにも繋がります。
ここでは、ビジネスや日常での印章・印鑑の効果的な使用法について、選び方、保管方法、注意点などを詳細に解説します。
1:選び方とその重要性
印章の選び方は、使用目的やシーンによって異なります。
ビジネスシーンでは、銀行印や実印など、法的効力を持つ重要な文書に使用する印鑑を慎重に選ぶ必要があります。
ここでのポイントは、素材の品質とデザインです。
例えば、木製や牛のツノ、チタンなど、様々な素材があり、それぞれ耐久性や印影の美しさに特徴があります。
また、日常生活では、簡易な認印を利用する場面が多く、こちらは手軽さやコストを考慮した選択が重要です。
2:保管方法とその重要性
印章の保管方法は、その状態を保つために非常に重要です。
特に、実印や銀行印などの重要な印章は、湿気や直射日光を避け、安全な場所に保管することが求められます。
また、盗難や紛失を防ぐために、鍵付きの印鑑ケースやセキュリティボックスの使用が推奨されます。
印鑑が損傷したり、不正使用されるリスクを最小限に抑えるためにも、適切な保管が必要です。
3:使用時の注意点
印章を使用する際には、いくつかの注意点があります。
特に、印鑑証明が必要な書類では、印影の正確さが求められます。
印章を使う際は、朱肉を均等に塗布し、はっきりとした印影が得られるように注意しましょう。
また、印鑑照合においては、印鑑証明書との印影の一致が重要です。
印鑑を使用する際には、その証明書との照合を意識することが大切です。
□印鑑の基礎とは?署名と捺印の違いから人生の節目での使用まで
印鑑は、私たちの日常生活やビジネスシーンで頻繁に使用される重要なアイテムです。
1:署名と記名
署名は、契約書のような重要な書類に本人が直接手書きする氏名のことで、個人の筆跡を証拠とするため、証拠能力が高くなります。
記名は自署以外の方法で氏名を記載する行為を指し、証拠能力は署名に比べて低いとされています。
しかし、押印を追加することで署名と同等の有効性を発揮します。
2:押印と捺印
押印と捺印には大きな違いはありません。
しかし、記名に加えて印鑑を押す場合は押印、署名に加えて印鑑を押す場合は捺印を用います。
日本では、署名に加えて捺印することが一般的で、法的な証拠能力を高めるために用いられます。
証拠能力が一番高いのは署名捺印です。
次に署名のみ、記名押印と続きます。
3:人生の節目での印鑑使用
出生届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、住民移動届、不動産の購入、死亡届など、人生の重要な節目で印鑑の使用が求められます。
これらの場面では、正式な効力を持つ実印や認印の使用が必要です。
基本的にシャチハタは認められていないため、正確な手続きを行うためには適切な印鑑の準備と使用が不可欠です。
4:印鑑偽造の罪と罰
印鑑の偽造や不正使用は法律で禁止されており、罪に問われる可能性があります。
偽造された印鑑を使用することは、本人の意思に反する契約の成立や、不正な取引の証明など、重大な法的な問題を引き起こす可能性があります。
印鑑は単なる文書の装飾ではなく、法的な意味を持つ重要なツールです。
署名と捺印の適切な使用、実印の管理、そして人生の節目での正しい印鑑使用法を理解し、適用することで、個人の権利を守り、法的な問題を未然に防ぐことにつながります。
印鑑に関する基礎知識を深め、正確な使用法を心がけましょう。
□印鑑を守る!高品質な印鑑ケースの重要性
大切な印鑑を守るためには、印鑑ケースの選び方が重要です。
適切な印鑑ケースを選ぶことで、印鑑の美しさと機能性を長期間保持できます。
1:印鑑ケースの種類と質感
印鑑ケースには、プラスチック製や金属製、木製などさまざまな材質があります。
木製のケースは、その温かみと自然な質感が特徴で、シンプルながらも高級感を感じさせます。
一方で、チタンや貴石、宝石を使った高級な印鑑ケースは、その素材感と耐久性で印鑑を守ります。
2:保管方法の重要性
印鑑ケースは単に印鑑を収納するためだけではなく、印鑑を衝撃や汚れ、湿気から保護する役割も担っています。
そのため、印鑑の素材や用途に合わせて、適切なケースを選ぶことが重要です。
また、定期的なメンテナンスや朱肉の交換も印鑑を長持ちさせる秘訣です。
3:朱肉の交換方法
印鑑ケースに付属している朱肉は、使用するうちに乾燥したり色が薄くなったりします。
朱肉は交換可能で、印鑑ケースを購入した店舗や印章専門店で交換用の朱肉を購入できます。
朱肉の交換は、清潔な印影を保持し、印鑑の美しさを長く維持するためにも定期的に行うことをおすすめします。
4:高級な印鑑ケースの利点
高品質な印鑑ケースを使用することで、大事な印鑑を物理的なダメージから守るだけでなく、所有する喜びも感じられます。
特に法人の実印のような重要な印鑑は、適切なケースで保管することでその価値を高め、安心して使用できます。
印鑑ケースは印鑑を保護するために欠かせないアイテムです。
素材、デザイン、機能性を考慮し、適切なサイズの印鑑ケースを選ぶことで、印鑑を長期間美しく保つことにつながります。
また、朱肉の適切な管理も重要で、印鑑の保護と使用の満足度を高めるためにも、高品質な印鑑ケースの選択をおすすめします。
□まとめ
今まで知らなかったハンコにまつわるマメ知識が得られたなら幸いです。
当社は、10年以上の経験を積んだ熟練彫刻職人による本格実印専門ショップで店頭の半額の価格で実印を提供しております。
実印をお探しの際はぜひご検討ください。